消費電力とは? 電気料金の計算方法や節約方法も併せて解説
投稿日:2025/04/01
更新日:2025/03/27

でんきの豆知識
近年、電気料金の値上がりが続いており、節電を意識している方も多いのではないでしょうか。しかし、月々の電気料金は分かっても、何にどのくらいかかっているのかはなかなか分からないものです。ご家庭の電気料金を正しく把握するには、電化製品ごとの消費電力に注目してみましょう。
本記事では、消費電力の概要や電化製品ごとの電気料金の計算方法を解説します。記事の後半では、消費電力を減らして電気料金を節約する方法もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
※本記事の内容は2025年3月時点の情報です

この記事を書いた人

- マーケティング室 室長
-
大学在学中、発展途上国でのボランティア活動がきっかけで
伊藤忠エネクスに入社。
入社後は一貫して電力ビジネスに携わり、電力ビジネス領域における大規模システム構築を実現。
電力のスペシャリストとして電力ビジネスの拡大に尽力している。
この人が書いた他の記事
目次
消費電力とは、電化製品を動かすときに使う電力のこと
まずは、消費電力という言葉の意味を理解しましょう。消費電力とは、その名の通り電化製品を動かすときに「消費」する「電力」のことです。消費電力の数値が大きければ、電化製品を動かす際に多くの電力が必要になるので、必然的に電気料金も高くなります。また消費電力は電化製品の種類やモード、機能によって異なるため、本体の表記や取扱説明書、メーカーのWebサイトなどを確認して、正確な数値を把握することが大切です。
消費電力と併せて「定格消費電力」や「年間消費電力量」などが記載されていることもあるので、それぞれの違いも解説します。
定格消費電力とは最大消費電力のこと
定格消費電力とは、電化製品を使用する際にかかる最大消費電力のことです。JIS規格が定める条件に基づいた方法で測定されます。照明器具や単純なオン・オフのみの機器などを除いて、電化製品が定格消費電力のまま稼働し続けることは基本的にありません。しかし、電子レンジや電気ヒーターのように、消費電力に幅がある電化製品は、最大出力時に他の機器との合計で契約アンペア数を超えてしまう場合があり、ブレーカーが落ちる原因になります。そのため、安定して電化製品を使うためにも定格消費電力を把握することは重要です。
年間消費電力量とは1年間に消費する電力の合計のこと
年間消費電力量とは、JIS規格の条件下で1年間電化製品を使い続けた場合の消費電力量です。冷蔵庫やテレビのように待機時と稼働時で消費電力に差がある製品や、エアコンのように消費電力が変動しやすい製品は、最小消費電力や定格消費電力だけでは実態に即した電気料金の算出が困難です。そのため、使用状況に近い条件で算出された年間消費電力量が、電気料金を算出する際の目安として役立ちます。電化製品を新たに購入する際は、年間消費電力量に注目するとおおよその電気料金を把握できます。
消費電力量とは一定期間に使われる電力量のことで、その瞬間に消費する電力を表す消費電力とは少し意味合いが異なります。
電気に関するさまざまな単位

電気を表す単位にはいくつか種類があります。消費電力から電気料金を計算したり、それぞれの関係性を理解したりするためにも、単位ごとの意味を把握しましょう。
V(ボルト)
V(ボルト)は電圧を表す単位です。電源がどれくらいの力で電流を流しているのかを表します。電圧を水槽に入っている水で例えてみましょう。一つは水位と水圧が低い水槽で、蛇口から一定時間に出る水の量は少ないです。一方、水位が高い水槽は強い水圧がかかるので、同じ大きさの蛇口であっても出てくる水の量が多いです。
電圧も同様に、圧力が強いと電気を押し出す力が強くなり、大きな電流が流れます。ボルトを計算する場合は、以下の計算式で算出できます。
- ボルト(V) = ワット(W) ÷ アンペア(A)
ちなみに、日本の家庭用コンセントは、100Vで統一されているのが一般的です。そのため多くの電化製品は、100Vで使用することを前提に作られています。
A(アンペア)
A(アンペア)は、流れる電気の量(電流)を表す単位です。流れる電流が大きいほど、消費電力の大きい電化製品を動かせたり、複数の機器を同時に使用できたりします。
こちらも水槽に例えてみましょう。蛇口の大きさによって流れる水の量は異なります。蛇口が小さい水槽は流れる水の量が少なく、蛇口が大きい水槽は流れる水の量が多くなります。
ご家庭の契約アンペア数が小さいと、同時に使用する電化製品の種類や数によっては、ブレーカーが落ちる可能性があります。
アンペアを計算する場合は、以下の計算式で算出できます。
- アンペア(A) = ワット(W) ÷ ボルト(V)
W(ワット)
W(ワット)は、1秒間に使われる電気エネルギーの大きさ(消費電力)を表す単位です。電化製品が稼働する際に必要な電力のことであり、ワット数が大きいものは多くの電気を消費します。こちらも水槽で例えてみましょう。水圧が低くて蛇口が小さい水槽は、蛇口から出る水の量も少ないです。一方、水位が高く蛇口も大きい水槽は、蛇口から出る水の量は多くなります。この水の量がワットです。
ワットを計算する場合は、以下の計算式で算出できます。
- ワット(W) = ボルト(V) × アンペア(A)
Wh(ワットアワー)
Wh(ワットアワー)は、一定時間当たりの消費電力量を表す単位です。ワットが瞬間的な消費電力を表すのに対して、ワットアワーは時間に応じた消費電力量を表します。電化製品の消費電力が小さくても稼働時間が長ければ消費電力量は大きくなり、消費電力が大きくても稼働時間が短ければ消費電力量は小さくなります。
こちらも水槽で例えてみましょう。桶にたまる水の量が1回当たり1リットルの場合、10回水を注ぐことでたまる水の量は10リットルです。桶にたまる水の量が1回当たり2リットルの場合、5回注ぐことでたまる水の量は10リットルです。どちらも同じ10リットルですが、1回当たりのたまる量と注ぐ回数が異なります。電気料金は、消費電力と使用時間の両方に影響を受けるため、どちらか一方だけではなく両方を考慮する必要があります。なお、ワットアワーは以下の計算式で算出できます。
- ワットアワー(Wh) = ワット(W) × 使用時間(h)
同じく、一定時間当たりの消費電力量を表す単位として、kWhもあります。こちらは1,000W(=1kW)の電力を一定時間使用したときの電力量です。ご家庭の電気料金を算出する際に用いられます。また1年間の消費電力量(期間消費電力量)を表す単位としても目にします。
電化製品を使用するときにかかる電気料金を計算してみよう

消費電力や年間消費電力量が分かると、電化製品ごとの電気料金を算出できます。まずは、ご家庭で使用している電化製品ごとに使用時間・頻度をリストアップしましょう。次に以下でご紹介する計算式で、電化製品ごとの電気料金を算出してみてください。電気料金で比較すると、無駄な電力消費に気付きやすく節電の対策を立てやすいです。
消費電力を基に計算する場合
消費電力は電化製品の本体や取扱説明書、メーカーのWebサイトなどで確認できます。この数値を基に電気料金を算出してみましょう。
計算式は以下の通りです。
- WをkWに変換:消費電力(W) ÷ 1,000
- 電気料金:消費電力(kW) × 利用時間 × 電力量料金単価(円/kWh)
電力量料金単価は、契約している電力会社によって異なります。検針票や電力会社のWebサイト、会員ページなどで確認できるので、チェックしてみてください。今回は、公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会が目安単価として設定している電力量料金単価:31円(/kWh)で算出します。
【前提条件】
- 消費電力:650W
- 電化製品の使用時間:2時間
- 電力量料金単価:31円/kWh
【2時間当たりの電気料金を算出する計算式】
- WをkWに変換:650W ÷ 1,000 = 0.65kW
- 電気料金:0.65kW × 2時間 × 31円/kWh = 40.3円
なお、取扱説明書に消費電力ではなく、定格消費電力のみが明記されている場合もあります。先述した通り、定格消費電力とは消費電力の最大値なので、電化製品を使用した場合にかかる最大の電気料金を算出できます。上記の計算式の消費電力の位置に定格消費電力を代入して、計算してください。
※参考:公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会.「よくある質問 Q&A」.https://www.eftc.or.jp/qa/?topics=1#qa3 ,(2025-03-19).
1カ月当たりの電気料金を計算する場合
前提条件の電化製品を1日2時間、1カ月(30日)使い続ける場合は、上記で算出した電気料金に日数を乗じます。
- 1カ月当たりの電気料金 = 40.3円 × 30日 = 1,209円
このように電化製品の使用時間や使用頻度、日数を乗じると、電気料金の目安を算出できます。他の電化製品も同じ方法で計算し、電気料金が高い機器から優先的に節電方法を検討しましょう。
年間消費電力量を基に計算する場合
エアコンや電子レンジのように、設定や使用条件によって消費電力が大きく異なる電化製品は、年間消費電力量を用いた方がより実際の使用状況に近い電気料金を把握できます。
年間消費電力量を基に電気料金を算出する際は、以下の計算式を使います。
- 1年間の電気料金 = 年間消費電力量(kWh) × 電力量料金単価(円/kWh)
例えば、年間消費電力量が1,500kWhの電化製品の1年間の電気料金を計算してみましょう。
- 1年間の電気料金 = 1,500kWh × 31円/kWh = 46,500円
このように、消費電力や年間消費電力量、契約している電力会社の電力量料金単価が分かれば、簡単に電気料金を算出できます。節電や電気料金の削減をしたい方は、現状を把握することから始めましょう。
代表的な電化製品の消費電力と電気料金の目安
忙しくてなかなか電気料金の計算ができない方向けに、ここでは代表的な電化製品の定格消費電力と、1時間当たりの電気料金をご紹介します。これに使用時間や回数を乗じれば、電化製品ごとの電気料金の目安が簡単に分かります。ただし、ここでご紹介する消費電力はあくまでも目安であり、実際の電気料金は機器によって異なる点にはご留意ください。
| 電化製品 | 定格消費電力 | 1時間当たりの電気料金 |
| 扇風機 | 34W | 1.054円 |
| パソコン | 45W | 1.395円 |
| 冷蔵庫 | 300W | 9.3円 |
| 洗濯機 | 400W | 12.4円 |
| 食器洗い乾燥機 | 900W | 27.9円 |
| 掃除機 | 1,000W | 31円 |
| ドライヤー | 1,000W | 31円 |
| 浴室乾燥機(電気式) | 1,290W | 39.99円 |
| 電子レンジ | 1,400W | 43.4円 |
| IHクッキングヒーター(1口) | 3,000W | 93円 |
※参考:東京都.「家庭の省エネハンドブック2024」.https://www.tokyo-co2down.jp/wp-content/uploads/2024/04/web_2024_handbook.pdf ,(2025-03-19).
【世帯別】月々の電気料金はいくら?
月々の電気料金は世帯人数やライフスタイル、住宅の性能などによって変わるため、ご家庭の電気料金が高いのか安いのかを判断するのは難しいものです。そこで東京都が「家庭の省エネハンドブック2024」内で明記している、戸建住宅と集合住宅の世帯人数別の電気料金をご紹介します。
【戸建住宅の世帯別電気料金一覧】
| 5月(気候が穏やかな時期) | 8月(冷房を多く使いやすい時期) | 1月(暖房を多く使いやすい時期) | |
| 1人世帯 | 5,857円 | 8,197円 | 11,739円 |
| 2人世帯 | 7,861円 | 11,638円 | 18,270円 |
| 3人世帯 | 8,546円 | 13,085円 | 19,394円 |
| 4人世帯以上 | 10,072円 | 15,194円 | 23,041円 |
【集合住宅の世帯別電気料金一覧】
| 5月(気候が穏やかな時期) | 8月(冷房を多く使いやすい時期) | 1月(暖房を多く使いやすい時期) | |
| 1人世帯 | 3,911円 | 5,850円 | 7,187円 |
| 2人世帯 | 6,153円 | 9,274円 | 11,939円 |
| 3人世帯 | 7,500円 | 11,643円 | 14,929円 |
| 4人世帯以上 | 8,561円 | 13,020円 | 16,431円 |
ここにある電気料金よりも月々の負担額が多い場合は、節電することで電気料金を削減できる可能性があります。次項で解説する節電術をぜひチェックしてみてください。
※参考:東京都.「家庭の省エネハンドブック2024」.https://www.tokyo-co2down.jp/wp-content/uploads/2024/04/web_2024_handbook.pdf ,(2025-03-19).
消費電力を減らして月々の電気料金を節約する方法

快適な生活を送る上で欠かせない電化製品ですが、使い方を見直すことで月々の電気料金を節約できる可能性があります。ここでは4つの節約方法をご紹介します。
使っていない電化製品のプラグを抜いて待機電力を減らす
電化製品は、電源プラグがコンセントに挿さったままになっていると、わずかな電力を消費します。これを待機電力といいます。待機電力は、リモコンで操作が行われたりタイマー予約の時間になったりしたときに、すぐに電化製品を稼働させるために使われています。
複数の電化製品で待機電力が発生してしまうと、月々の電気料金が少しずつですが値上がりしてしまうので、使わないときはプラグを抜く習慣を身に付けることが大切です。
電化製品の使い方を見直す
先述の通り、電化製品の消費電力は設定や使用条件によっても異なります。機器の使い方を工夫することで消費電力量を抑えられれば、電気料金を今よりも削減できる可能性があります。以下のような節電につながるポイントを毎日の生活で心掛けましょう。
- タイマー機能を使って自動的に電源をオフにする
- 冷蔵庫は過度に冷える温度設定にしない、頻繁に開閉しない
- 洗濯物はなるべくまとめて洗う
- 省エネモードがあれば、積極的に使う
- ホットカーペットを利用する人数が少ない場合は、全面モードを半面モードに変える
- 電力量料金単価が安い時間帯に、消費電力の大きい電化製品を利用する
省エネ家電に買い替える
省エネ家電とは、従来の製品よりも消費電力を抑えた設計や機能を持つ電化製品のことです。古い電化製品と同じ使用時間・頻度で使用していたとしても、電気料金を抑えられます。2013年と2023年に販売された機器の年間消費電力量と、見込まれる削減金額の一例を見てみましょう。
| 電化製品 | 2013年に販売した機器の 年間消費電力量 |
2023年に販売した機器の 年間消費電力量 |
1年当たりの削減金額 |
| 冷蔵庫 | 370~410kWh | 267kWh | 約3,190~約4,430円 |
| エアコン(8畳~12畳) | 903kWh | 769kWh | 約4,150円 |
| 温水洗浄便座(貯湯式) | 173kWh | 160kWh | 約400円 |
このように、10年で電化製品の省エネ性能は向上しています。そのため、省エネ家電に買い替える方が月々の電気料金は削減できる可能性が高いです。買い替え時の初期費用はかかりますが、長期的に見れば電気料金の節約につながるため、検討する価値はあるでしょう。
※参考:一般財団法人 家電製品協会.「省エネ家電で温暖化防止」.https://shouene-kaden2.net/learn/ ,(2025-03-19).
電力会社を見直す
ここまで消費電力や消費電力量を抑える方法をご紹介しましたが、電力量料金単価を下げることで電気料金を抑える方法もあります。
2016年の電力小売全面自由化以降、需要家は契約する電力会社を自由に選べるようになりました。中には基本料金や電力量料金単価の安さが特長の電力会社もあるので、気になる会社や料金プランを比較してみてください。
しかし、多くの新電力が参入したりさまざまな料金プランが登場したりしているものの、どのように比較検討したらよいのか分からず、これまでの契約を続けている方もいるでしょう。そのような場合は、各電力会社が提供する料金シミュレーションを活用するのがおすすめです。料金プランを切り替えることで、どれくらいの電気料金の削減効果が見込めるのかを確認できるものもあります。
金額以外の部分でも電力会社をしっかり比較したい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。新電力15社の特長や電力会社を選ぶ際のチェックポイントを解説しています。
▼おすすめの新電力15選! 固定単価プランと市場連動型プランの両方の電力会社をご紹介!
まとめ
私たちが普段何気なく使っている電化製品は、一つひとつ異なる消費電力で動いています。月々の電気料金の値上がりで悩んでいるなら、電化製品ごとの消費電力や電気の仕組みを正しく理解して、使い方や使用頻度を見直すことが大切です。
電気料金を減らすには、待機電力を減らしたり省エネ家電に切り替えたりといった方法が有効ですが、電力会社を切り替えるという手もあります。電力会社を見直して電気料金の削減をしたいなら、エネクスライフサービスが提供するTERASELでんきがおすすめです。
TERASELでんきは、電気の使い方によって以下の4つのプランから適したものを選べます。
- TERASELプラン:電気使用量に応じて電力量料金が変動する従来の料金プラン。使用量が少ない方向け
- 超TERASELプラン:電気使用量に応じて電力量料金が変動する従来の料金プラン。使用量が多い方向け
- TERASELマーケットプラン:市場価格に合わせて電力量料金単価が変動するプラン。電気の使い方を工夫できる方向け
- TERASELマーケットあんしんプラン:市場価格に合わせて電力量料金単価が変動、かつ上限が設けられているプラン。節約をしつつも電気料金の高騰リスクをなるべく抑えたい方向け
無理なく電気料金を削減したい方は、TERASELでんきへの切り替えを検討しましょう。
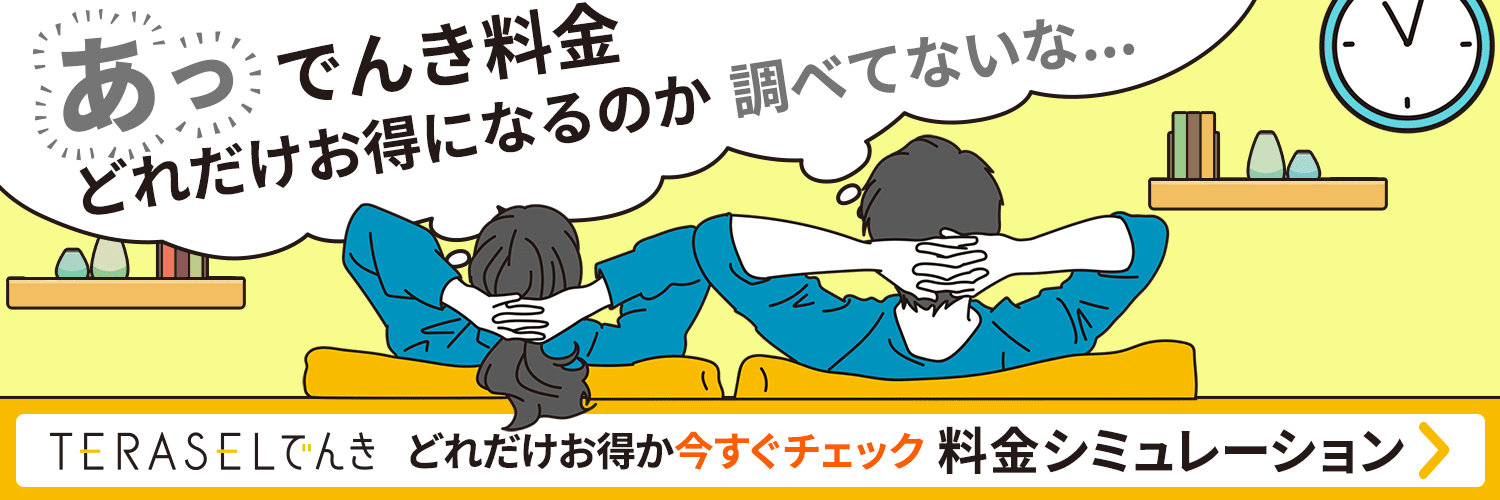
関連記事









