【種類別】ブレーカーが落ちたときの原因と対処法は? 落とさないためのポイントもご紹介
投稿日:2025/04/01
更新日:2025/03/26

でんきの豆知識
複数の電化製品を同時に使用すると、ブレーカーが落ちてしまうことがあります。ブレーカーが落ちるのにはいくつかの原因があり、安全に生活するためには原因別に正しく対処することが重要です。
本記事ではブレーカーが落ちたときの原因と対処法を種類別にご紹介します。またブレーカーを落とさないためのポイントもお伝えするので、何度も電気が使えなくなって困っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
※本記事の内容は2025年3月時点の情報です

この記事を書いた人

- マーケティング室 室長
-
大学在学中、発展途上国でのボランティア活動がきっかけで
伊藤忠エネクスに入社。
入社後は一貫して電力ビジネスに携わり、電力ビジネス領域における大規模システム構築を実現。
電力のスペシャリストとして電力ビジネスの拡大に尽力している。
この人が書いた他の記事
目次
ブレーカーの役割と種類

まずはブレーカーの役割と種類について解説します。電気は、玄関や勝手口、洗面所などに設置されている四角いボックス「分電盤」を介して、住宅内の各部屋に供給されるのが一般的です。
分電盤は、いくつかのブレーカーやボタンなどで構成されています。ブレーカーは分電盤に組み込まれた装置の一つであり、安全に電気を使用するために必要なものです。何らかの異常を検知すると電気を遮断し、機械の故障や事故を防ぐ役割があります。
なお、ブレーカーは以下の3種類に分けられます。
- アンペアブレーカー
- 漏電ブレーカー
- 安全ブレーカー
それぞれ役割が異なるので、以下で詳しく見ていきましょう。
アンペアブレーカー
アンペアブレーカーの役割は、電力会社と契約している以上の電気が流れないようにすることです。分電盤の左側に配置されていることが多く、電力会社によっては「リミッター」や「電流制限器」、「サービスブレーカー」、「契約ブレーカー」という名称で呼ばれている場合もあります。
電力会社と契約している、一度に使用できる電気の量を契約アンペア数といいます。契約アンペア数の上限を超える電流が流れたとき、アンペアブレーカーは電気を遮断。全ての部屋で電気が使えなくなります。
分電盤のアンペアブレーカーの近くには「30A」「40A」といった数字が記載されており、この数字が契約アンペア数を指しています。40Aと表示がある場合は一度に40Aを超えた電流が流れると、アンペアブレーカーが落ちる仕組みです。
スマートメーターを導入している場合
近年では「スマートメーター」を導入している家庭も増えてきています。スマートメーターとは、30分ごとの電気使用量を計測し、遠隔で自動検針ができる電力量計のことです。アンペアブレーカーの機能も搭載されているため、スマートメーターを導入している場合は分電盤にアンペアブレーカーが取り付けられていないのが一般的です。
漏電ブレーカー
漏電ブレーカーの役割は、漏電による感電や火災などの事故を防ぐことです。基本的には、分電盤の中央に配置されています。漏電ブレーカーの近くには「漏電ブレーカー」と明記されていることが多いので、他のブレーカーと見分けがつきやすいでしょう。電力会社によっては「漏電遮断器」と呼ばれているケースもあります。
漏電ブレーカーは住宅の電気回路内で漏電を検知すると、電気を遮断する仕組みになっています。住宅全体で電気が使えなくなるので、感電や火災が起きるリスクを抑えられます。人の命に関わる恐れもあるので、漏電ブレーカーが落ちたときには、速やかに、かつ適切に対応しなければなりません。
安全ブレーカー
安全ブレーカーの役割は、各部屋の電気の供給量を管理することです。一般家庭に供給されている電気は、部屋ごとにアンペア数の上限が決められています。各部屋で決められたアンペア数を超えた電流が流れると、安全ブレーカーが落ちる仕組みになっています。安全ブレーカーが落ちた場合、アンペア数を超えた部屋だけ電気が使えなくなります。
なお、安全ブレーカーは分電盤の右側に配置されていることが多く、部屋ごとに小さめの専用のブレーカー(スイッチ)が付いています。電力会社によっては「子ブレーカー」や「分岐ブレーカー」と呼ばれるケースもあります。
【種類別】ブレーカーが落ちたときの原因と対処法

ブレーカーが落ちたときの原因や適切な対処方法は、ブレーカーの種類によって異なります。そこで、ここからはブレーカーの種類ごとに詳しい対処法を解説します。
なお、夜間にブレーカーが落ちた場合、周囲が真っ暗な状態になります。暗い部屋を移動すると転倒リスクが高まるため、懐中電灯などを持って分電盤が設置されている場所に移動しましょう。また絶対にブレーカーはぬれた手で触らないでください。感電するリスクがあるため、タオルで手を拭いたり、ゴム手袋などをはめたりしてから対応しましょう。
アンペアブレーカーが落ちたときの原因
アンペアブレーカーが落ちてしまった場合は、一度に多くの電気を使い過ぎたことが主な原因です。先述した通り、契約アンペア数の上限を超えた電流が流れると、アンペアブレーカーは落ちてしまいます。例えば、契約アンペア数が30Aの場合は、住宅内で同時に使える電気は30Aまでということです。一度に合計で30Aを超える電流が流れると、安全ブレーカーが落ちて住宅全体が停電してしまいます。
ドライヤーやエアコン、オーブントースターといった、消費電力の大きい電化製品を同時に使用する場合は安全ブレーカーが落ちやすいので注意が必要です。
対処法
アンペアブレーカーが落ちたときは、それまで使用していた電化製品の電源を切ったりコンセントを抜いたりしましょう。その後、「オフ(切)」の状態になっているアンペアブレーカーのスイッチを「オン(入)」に戻せば、電気が復旧します。
もし、アンペアブレーカーのスイッチをオンにしてから10秒ほど時間が経過しても電気がつかない場合は、アンペアブレーカーではなく漏電ブレーカーが落ちている可能性が高いです。アンペアブレーカーの右横にある、漏電ブレーカーの状態を確認してください。
なお、スマートメーターを導入しているご家庭では、電気の使い過ぎで契約アンペア数の上限を超えた電流が流れた場合でも、10秒後には自動復旧するのが一般的です。ブレーカーが落ちてから10秒以上たっても自動復旧しない場合は、漏電ブレーカーが落ちている可能性があるため、分電盤を確認しましょう。
漏電ブレーカーが落ちたときの原因
漏電ブレーカーが落ちてしまった場合は、その名の通り漏電が主な原因です。住宅内にある配線が劣化していたり、使用している電化製品の回路・コードが破損していたりする可能性があります。
繰り返しになりますが、漏電ブレーカーが落ちた場合は感電や火災のリスクがあるため、そのまま放置せず、漏電が疑われる回路を速やかに見つけなければなりません。
対処法
漏電ブレーカーが落ちた場合は、以下の手順で対処しましょう。
- 分電盤でアンペアブレーカーがオンに、漏電ブレーカーがオフの状態になっていることを確認する
- 安全ブレーカーのスイッチを全てオフにする
- 漏電ブレーカーをオフからオンにする
- 安全ブレーカーには複数のスイッチがあるので、スイッチを一つずつオンにする(漏電した回路がある部屋のスイッチをオンにしたタイミングで、漏電ブレーカーが落ちる)
- 全ての安全ブレーカーのスイッチを、再度オフにする
- 漏電ブレーカーのスイッチをオフからオンにする
- 4で確認した、漏電している部屋以外の安全ブレーカーのスイッチをオンにする
- 4で確認した、漏電している部屋で使用している電化製品のコンセントを抜く
安全ブレーカーのスイッチを一つずつオンにしていくと、どこかのタイミングで漏電ブレーカーが再び落ちる可能性が高いです。これにより、漏電ブレーカーが再び落ちた部屋の電気回路が漏電していることが分かります。漏電している部屋が分かったら、ご自身で対処しようとせずに、早急に電力会社や専門業者に点検・修理を依頼してください。
安全ブレーカーが落ちたときの原因
安全ブレーカーが落ちてしまった場合は、対応している部屋で一度に多くの電気を使い過ぎたことが主な原因です。
安全ブレーカーには、それぞれの部屋のアンペア数の上限が記載されているものがあります。例えば、記載されたアンペア数が10Aである場合、その部屋で同時に使用できるのは合計で10Aまでです。10Aを超えた電流が流れると、安全ブレーカーが落ちてしまいます。
部屋ごとのアンペア数は住宅全体の契約アンペア数よりも少ないため、同時に多くの電化製品を使うときは注意してください。また部屋によってもアンペア数の上限は異なるため、一度、契約内容を確認しておくのがおすすめです。
対処法
安全ブレーカーが落ちたときの対処法は、基本的には先述したアンペアブレーカーの場合と同様です。安全ブレーカーが落ちた部屋でそれまで使用していた電化製品の電源を切ってから、安全ブレーカーをオンにしましょう。
電気が復旧したら、使用する電化製品の数を減らしてください。安全ブレーカーが落ちる直前と同じように電化製品を使うと、再びブレーカーが落ちてしまう可能性があります。
ブレーカーが落ちる原因が分からない場合
同時に多くの電化製品を使っていなかったり漏電が起きていなかったりするにもかかわらず、ブレーカーが落ちることもあります。その場合は、ブレーカーそのものに不具合や故障が起きているかもしれません。
社団法人日本電機工業会によると、ブレーカーの交換推奨時期は15年とされています。長期間ブレーカーを交換していない場合は、経年劣化によって不具合を起こしていたり故障していたりする可能性があります。ブレーカーが落ちる原因が分からない場合は、契約している電力会社や専門業者に連絡をして、点検してもらいましょう。
※参考:社団法人日本電機工業会.「産業用配線用遮断器 漏電遮断器 更新ガイダンス」.https://www.jema-net.or.jp/jema/data/2009circuit_breaker.pdf ,(2025-03-12).
周辺一帯が停電している場合は復旧まで待つ
ブレーカーが落ちた原因が分からないとき、ご自身の住宅だけではなく周辺一帯が停電していることもあります。その場合は、以下のような原因が考えられます。
- 電柱や配電設備の点検・設置を目的とした計画停電
- 自然災害や事故による停電
これらが原因の場合、基本的には電力会社の復旧対応を待つしかありません。計画停電の場合は、事前に家のポストに告知のチラシが入っているケースが多いです。また電力会社の供給エリアで起こっている停電の場合、電力会社のWebサイトで停電している地域や状況を確認できます。
ブレーカーを落とさないようにするためのポイント

アンペアブレーカーや安全ブレーカーが落ちた場合、先述した方法で対処すれば再び電気を使えるようになります。しかし、高い頻度でブレーカーが落ちると、日常生活に支障を来す上に、電化製品が故障する原因にもなりかせません。
また先述した通り、漏電すると感電や火災が起こるリスクも高まるので、漏電が起こらないように日頃から意識して電気を使うことが大切です。ここからはいくつかのポイントをご紹介します。
消費電力が大きい電化製品を同時に使わない
電化製品を同時に使い、契約アンペア数を超えた電流が流れるとブレーカーが落ちてしまいます。特に消費電力が大きい電化製品は、なるべく時間差で使うようにしましょう。例えば、夜の時間帯に夕飯作りと家族の入浴が被ると、電子レンジと電気ポット、ドライヤーなどを同時に使用する可能性があります。それぞれ消費電力が大きいので契約アンペア数によっては、ブレーカーが落ちてしまうかもしれません。
なお、契約アンペア数の単位はA(アンペア)で表しますが、電化製品の消費電力を表す単位はW(ワット)です。アンペア数は1秒間に流れる電気の量(電流)、ワット数は実際に消費される1秒間当たりの電気エネルギーを表しています。
アンペアとワットは、以下の計算式で算出可能です。
- アンペア(A) = ワット(W) ÷ ボルト(V)
- ワット(W) = アンペア(A)× ボルト(V)
ボルトとは電圧のことです。一般家庭の電圧は100Vなので、契約アンペア数が30Aの場合、消費電力が合計で3,000W以内に収まる電化製品であれば同時に使用できることが分かります。反対に消費電力が1,000Wの電化製品を3つ以上同時に使用すると、ブレーカーが落ちてしまうので注意しましょう。
ブレーカーを落とさないためには、お使いの電化製品の消費電力を把握しておくことも大切です。消費電力が大きい主な電化製品は以下の通りです。
- エアコン
- 電気ストーブ
- オーブン
- 電子レンジ
- ドライヤー
- 電気ポット など
ただし、上記に挙げた電化製品でも、メーカーやサイズ、機能によって消費電力は異なります。お使いの電化製品の消費電力を知りたい場合は、本体に張り付けられたシールや取扱説明書を確認してください。
※参考:東京電力パワーグリッド株式会社.「ボルト・アンペア・ワット」.https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/for-general/basic-knowledge/v_a_w.html ,(2025-03-12).
コンセントを分けて使う・増設する
パソコンとプリンター、炊飯器と電子レンジといったように、同じタイミングで使うことが多い電化製品の場合、作業しやすいように一つのコンセントにつないでいる方もいるのではないでしょうか。しかし、一つのコンセントに電流が集中していると、定格容量を超えやすくなり安全ブレーカーが落ちてしまいます。
先述したような消費電力が大きい電化製品をどうしても同時に複数使いたい場合は、電化製品の配置を見直した上で、コンセントを分けましょう。コンセントが足りない場合は、専門業者に依頼をしてコンセントを増設するのも方法の一つです。
漏電対策をする
漏電は、感電や火災のリスクがある危険な現象です。漏電を発生させないように、日頃から以下の2点の対策をしましょう。
タコ足配線をやめる
タコ足配線とは、市販の延長コードや電源タップを使ってコンセントの挿し口を増やした配線状態です。
タコ足配線は、1つのコンセントに複数の電化製品をつなげられる分、発熱・発火の原因となる恐れがあります。例えば、15Aが上限のコンセントに延長コードをつなぎ、600Wのこたつと500Wのホットカーペット、700Wのホットプレートを同時に使用すると、合計1,800Wとなりコンセントの上限の15A(1,500W)を超えてしまいます。過剰な負荷がかかるため、コンセントやコードが発熱・発火し、火災が起こりやすくなるリスクがあるのです。
なるべくタコ足配線を控え、どうしても使用する場合はコンセントの定格容量を超えないように注意しましょう。
アース線を正しく取り付ける
冷蔵庫や電子レンジ、洗濯機といった、水回りや湿気が多い場所で使う電化製品には、アース線と呼ばれるものが付いています。アース線は、電源プラグに接続されているケーブルです。万が一漏電してしまった場合に電流を地面に逃がす役割があり、感電や火災の事故を防ぎます。
アース線が適切に取り付けられていなかったり、劣化・損傷したりしていると、万が一漏電してしまった際に重大な事故につながりやすいです。それぞれの電化製品の取扱説明書を確認した上で、必ず正しく取り付けるようにしてください。
契約アンペア数を変更する
電化製品の使い方に気を付けたりコンセントを分けて使ったりしても、頻繁にブレーカーが落ちてしまう場合、契約アンペア数を見直すのも選択肢の一つです。
実際にご家庭で使用している電化製品の数や消費電力を洗い出し、一番電気を多く使うシーンでもブレーカーが落ちないように、適切な契約アンペア数を決めましょう。冷暖房器具をつけっ放しにする季節や、一日のうち電気を最も多く使う時間帯でもブレーカーが落ちないように試算するのがポイントです。
まとめ
ブレーカーにはアンペアブレーカーと漏電ブレーカー、安全ブレーカーの3種類があり、それぞれ役割や落ちてしまったときの対処法が異なります。ブレーカーが落ちた際には、慌てずに原因を特定し、適切な対処を行いましょう。
また日頃からブレーカーを落とさないための対策を講じることも大切です。消費電力の大きい家電製品の同時使用を避ける、漏電対策をする、契約アンペア数を変更するといった方法を実践してみてください。
さらに、電気を多く使うご家庭は、ブレーカーが落ちやすいだけではなく、電気料金が高くなりやすい傾向にあります。電気料金を削減したいなら、契約アンペア数の変更に併せて電力会社を切り替えるのも方法の一つです。
エネクスライフサービスが提供する「TERASELでんき」では、電気使用量が多い方向けの「超TERASELプラン」や、電気の使い方を工夫できる方向けの「TERASELマーケットプラン」など、4つの料金プランを提供しています。ライフスタイルに合わせて料金プランを選ぶことで、無理なく電気料金を節約できるでしょう。
契約時にはPayPayポイントやAmazonギフトカードといった6つの特典の中から好きなものを選べる他、毎月の電気料金に応じて楽天ポイントももらえます。現在の電気料金と比べてどのくらい節約できるのか、ぜひ料金シミュレーションでチェックしてみてください。
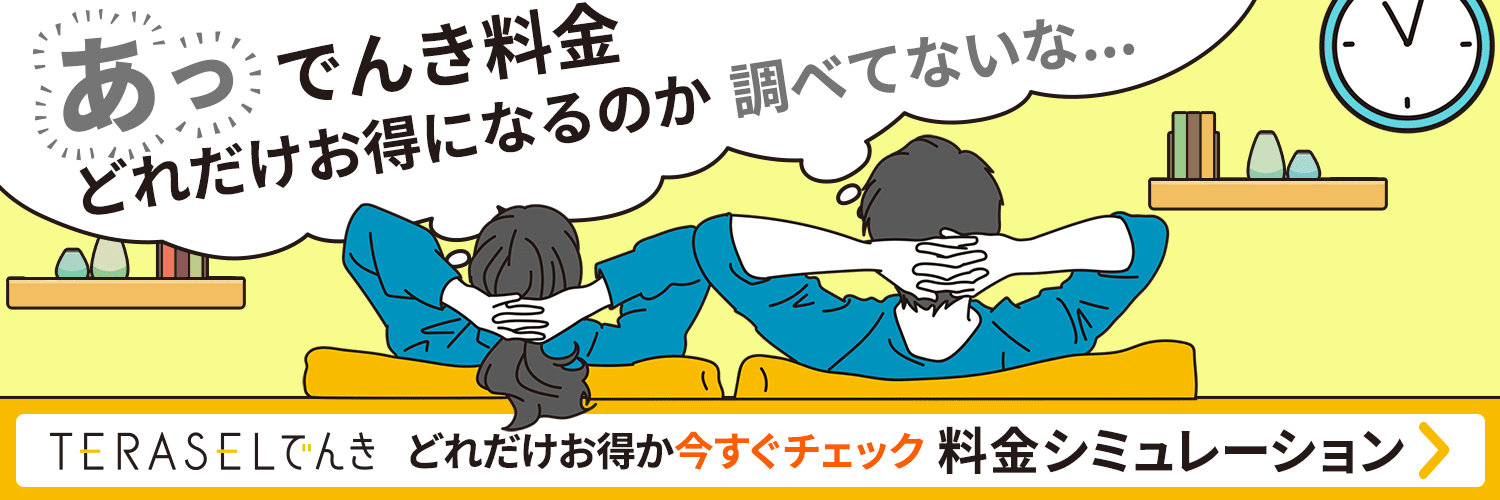
関連記事









